2009年9 月 4日 (金)
2009年5 月27日 (水)
2009年4 月18日 (土)
救急法基礎講習会
今日、救急法基礎講習というのを受けてきました。
今度試験を受ける、ピラティスインストラクターの認定のために。
アメリカに本部のある協会だからか、それとも昨今は、日本でも、フィットネスの世界ではもはやあたりまえなのかどうか、とにかく現行の心肺蘇生法(CPR)の知識があることが認定要件で、そのあたりはしっかりしているということでしょうか。
考えてみれば、人の心拍数を少なからず上げるような運動をさせようというのですから、当然といえば当然か・・・。
とにかく、そんな、申し訳ないような自分本位の理由で受講したわけですが・・・。
基礎講習なので、一次救命を教えてもらいました。
気道確保、体位の変え方、心肺蘇生法、AEDの使い方などなど。
細かいことは申しませんが、受けて見て、この知識を知っている人が多い方がいいな、と、単純に思いました。
一緒にチームを組んだ人たちも同様の感想を持ったようでした。
どうしてかというと、
第一発見者は、手助けをしてくれる人を呼ぶのが基本。
一人では、できることはとても限られてしまうんです。
数人で協力して、救急隊に引き継ぐまで、できることを行うのが一次救命。
そして、手伝ってくれる人が、自分と同様の知識を持っていればいいけれど、そうでない場合は、なかなか厳しい状況になります。
少なくとも、自分のほかにあと一人、心肺蘇生法の知識がある人がかけつけてくれるといい。
心肺蘇生法は、救助者の方も、体力をかなり消耗するんです。
救急隊に引き継ぐまでの何分間か、二人で交代しながらなら、心肺蘇生法を絶え間なく続けられる可能性が高い。
それで、「みんながこの知識を持っているといいよね」という感想になったわけです。
現実的にそういう場面に出くわして、はたしてパニックを起こさずに動けるのかどうか。
その時、自分は勇敢に行動できるんだろうか。
でも、何も知らないよりは、知っている方がきっと、はたと我に返って、すべきことができるのかも。
もし、ご興味がおありなら、お近くで機会があれば、ぜひ。
難しいことではないですが、知らなければできないことですので。
そういえば、今日は男性の方が8割ぐらいだったかな~。男性の方が、こういう意識が高いのかもしれないですね~。
2009年4 月16日 (木)
最近走ってないんです。
最近走っていないので、このブログもなかなか記事をアップできません。
大好きな自転車にも乗らずに、いったい、なにをしているかというと・・・。
実は、ピラティスのインストラクターの勉強をしています。![]()
ピラティスレッスンクラブというのを主催していますが、ずっとお願いしていたインストラクターの方のご都合がつかなくなたので、やむを得ず、というのが正直なところです。
これから若くなることはないんだし、自分の為にも、家族や友人知人の為にもなるかと思って、相当迷いましたが、ついに決心して、ある協会の国際認定をとることにしました。
まぁぁぁぁぁぁ、きついこときついこと。![]()
覚悟はしていましたが、なんというか、この歳で、この体力で、とんでもないことを始めたんではなかろうかという「やらかしちゃった」感満点。
3年ほど、ピラティスを教えてもらっていましたが、インストラクターとなると話は別でございます・・・。
本当に認定がとれるんでしょうか、私・・・。![]()
心優しい友人たちに練習用のボディーになってもらって、四苦八苦。
(皆さん、感謝っ!)
一番の犠牲者の鬼コーチ(夫)には、自転車の時の仕返し、
あ、いえいえ![]() 、
、
お礼も兼ねて、ほぼ毎日ボディーになってもらっていて、繰り返される容赦ない指導のせいか、なんだかずいぶん姿勢が良くなり丈夫になったご様子で・・・。
今月末に、いよいよ認定試験があり、数か月にわたる勉強も、そろそろラストスパート。![]()
そんなわけで、いろんなことがそっちのけです。
体力にはわりと自信がある方ですが、ついに体力勝負になりそうです。
しばらくは、更新がぼちぼちになるかもしれませんが、どうぞ忘れないでやってくださいませ。
これが終わったら、走りますよ~!!![]()
2009年3 月18日 (水)
自転車利用と道路に関する意見募集
国土交通省と警視庁が、自転車利用と道路に関する意見を募集しているのを見つけました。
アンケート形式です。
様々な立場の人の、あらゆる意見が集約されて、
自転車が加害者にも被害者にもなることなく、
安全に走れる道路がたくさんできるといいな~と思い、回答してみました。
おひとつ、いかがですか?![]()
国土交通省・警視庁:自転車利用と道路に関する意見募集
http://road-safety.jp/
2009年1 月29日 (木)
2009年1 月 7日 (水)
あけましておめでとうございます!
寒い中を、さっそうと走っておられる皆様!!
あけましておめでとうございます。
自転車関連の記事が一向にかけない今日この頃、
ちなみに、私目のお正月は、と言いますと、
実家に帰り、
おせちを食べて
子供のころから慣れ親しんだ、近所の神社に初詣
あちこちで、お酒を勧められるままに頂きまして
(えぇ、えぇ、そりゃーお断りするのは失礼でございますもの)
こっちに帰ってきてからは、山梨は身延山久遠寺へ行ってきました。
なんでも、出来立てほやほやの五重塔は、5月に落慶法要があるそうで。
新品の割には、かなりシックな色合いです。こういうものを作る技術って、まだちゃんとあるんだなぁ~。
そういえば、今年は善光寺も御開帳。
お寺関係が熱い年ですね~。
寒がりの根性無し。
自転車の技術よりもずいぶん先に、落とすのが難しそうなお肉が付く予感。
初自転車は、いつになることやら・・・。
こんな私ですが、今年もどうぞ、よろしくお付き合いくださいませ。![]()
2008年12 月11日 (木)
フィーメールアスリートバイブル
フィーメールアスリートバイブル (編著)鳥居 俊
とってもきびしい通信講座の卒論の提出を前にして四苦八苦しながら、いくつか本を読んでいますが![]() 、その中の一冊。
、その中の一冊。
まあ、なんというか、目から鱗の話ばかり。
スポーツをしている女性や、女性と一緒にスポーツを楽しもうとする心優しき男性諸兄にもぜひ、読んでいただきたいところですが、自分で選んでおきながら、専門医学用語山盛りで、ちなみに私は、おなかいっぱいです。![]()
「男女には、差別はいらないけれど、区別は必要」
そういえば、雇用機会均等法施行当時は、そんな言葉、結構きかれましたっけ(歳がばれますねぇ)。それはもう、耳にタコができるほど。
関節の柔らかさ、骨格の違い、臨床的な故障部位の男女差。この本の中で開示される事実は、すでに私たちが感覚的に知っていることだけれど、改めて冷静なデータとして突きつけられると、びっくりしつつも、あぁ、やっぱりそうなんだと思います。
女性スポーツ医学という分野、まだまだ発展途上だそうです。
スポーツをする上で、女性がなにかとawayな感じは、今のところ仕方がない。そのわけも、著者なりの意見がそこここに散りばめられています。かなり現状に厳しい意見とも思いますが、女性アスリートたちの痛みと苦しみに接し、診察し続けた著者が受け取った彼女たちの叫びなのでしょう。
越えられないものは、現実にある。
女性アスリートは、いわば、スポーツという男性文化に飛び込んだ異端者であり、男女の境界を越境した侵入者である。そこにこそ、女性アスリートが直面する多くの問題の根源がある。(「フィーメールアスリートバイブル」より)
私は、自転車が大好きで、趣味で乗っているだけですけど、自転車をスポーツとしてとらえた時には、この意見はとても重いと感じます。
・・・・。
はっ・・・!
っていうか、間に合うのか、卒論・・・???
撮影:iPhone
2008年10 月22日 (水)
卒論のテーマ
プロフィールをご覧いただいた方は、お気づきかもしれませんが、
小さなハーブショップをやっております。
スキルアップのために、通信講座を受けていました。
薬用植物や医療の知識はもちろん、月に2冊の、さまざまな課題図書を読んで設問に答えたりと、かなり骨のある講座でした。
課題図書には哲学書や解剖学もあり、眠気と戦うこともしばしば・・・。
こんなことは、ん十年前、学校を卒業して以来でした。
1月に卒論の提出があるのですが、テーマを決めかねていました。
なにか疾患をテーマにすることも考えましたが、もうすこし視点を変えてみたいなぁと思っていました。
ハーブやアロマテラピー、なんていうと、なんだかすごくおとなしい感じがあるのも、正直なんとかならないものかと、かねがね思っていたというのもあります。
明るくエネルギッシュな側面もあるのに。
自分が、まさにこの時期に、自転車というものに出会ったのも何かの縁。
考えをまとめるよい機会なので、ずばり、決めました(ま、まさかっ![]() )
)
「サイクリスト(スポーツマン)と植物療法(仮題)」
ずばりという割に、かっこが多いですけど・・・。
本気?本気ですよ~。
こんなこと、誰も書いてないっしょ~(当たり前だよ~、おい![]() )
)
卒論が完成して、皆様のお役に立ちそうなものがあったら、順次アップしてみます。
卒論かぁ、と、ちょっと気がめいっていたのですが、なんだか楽しくできそうな気がしてきましたよ~(早くも空回りの予感が・・・)。









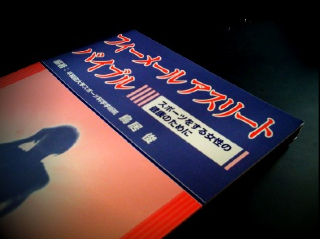

最近のコメント